お悩み解決室
公開 / 最終更新
看護におけるQOLとは?QOLを高めるケアに必要な4つの視点や実践方法を解説

「現場でよく聞くQOLって何?」「QOLを向上させるにはどのようにすればいいの?」と疑問に思う看護師も多いのではないでしょうか。
近年、少子高齢化の進行も相まって、複合的な慢性疾患をもつ高齢患者が増加しています。これにより、医療においては「治す医療」から「治し、支える医療」へのシフトが求められ、その中心となる考え方がQOL(生活の質)を意識した看護の実施です。
本記事では、QOLを高める看護の基本的な考えや、QOLの向上に必要な4つの視点、実践例について解説いたします。病院勤務の方や訪問看護師の方も、ぜひ参考にしてください。
2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方
目次
QOL(クオリティ・オブ・ライフ)とは

QOLとは“Quality of Life”の略で、「生活の質」や「人生の質」と訳されます。WHO(世界保健機関)は、QOLを次のように定義しています。
個人が生活する文化や価値観のなかで、目標や期待、基準または関心に関連した自分自身 の人生の状況に対する認識
つまり、QOLの高さや低さは、個人の価値観や背景に基づく主観的な認識によって決まります。生活の充実度や満足度は人それぞれ異なるため、医療においては患者本人の人生における価値観を考慮し、自ら治療法などを選択できるよう支援する姿勢が重要になります。
看護の現場でQOLが重要視される理由
看護の現場では、患者のQOLに配慮した支援がますます重要になっています。特に、慢性疾患や終末期ケアの場面において、人生の質を尊重し、その人らしい生き方に寄り添った看護を目指す方向へシフトしつつあります。
また、少子高齢化の進行により、療養の場を医療機関から自宅など地域へと以降する動きが加速していることも、QOLを重視する理由の一つです。
そのような時代の中で看護師が担う役割は、患者の治療のみに注力するのではなく、疾患と向き合いながら生きる過程を一緒に考え、ケアに反映させていくことにあります。
患者の社会的背景や生活環境にも目を向けて支援していく必要があり、より専門的な視点と実践力が求められます。
参考:日本看護協会「2025年に向けた看護の挑戦 看護の将来ビジョン いのち・暮らし・尊厳を まもり支える看護」
QOLとADLの違いと関係性
QOLを考えるうえでは、ADLとの違いや関係性を理解する必要があります。ADLは“Activities of Daily Living”の略で「日常生活動作」と訳されます。歩く、食べる、座るといった生活に必要最低限な動作を指します。
医療や介護の現場では長らく、リハビリによってADLを高めることがQOLの向上につながるとされてきました。しかし、医療機器や補助具の進歩により、近年では「ADLの改善=QOL向上」とは限らないという認識が広がっています。
たとえば、在宅酸素療法や人工呼吸器、電動車いす、歩行器、電動ベッドなどの補助機器を活用すれば、ADLが制限されていても本人の希望に沿った生活を送ることが可能です。
患者が「できること」だけに注目するのではなく、「本人が望む生活をどう実現するか」という視点で支援することが大切になります。
QOLの評価方法
QOLは主観的な感覚であるため、客観的に評価することが大切です。代表的な評価方法には、以下のようなものがあります。
【SF-36®(MOS 36-Item Short-Form Health Survey)】
SF-36は1980年代にアメリカで作成された評価方法で、身体面と精神面から構成された36個の質問に答えていく形式です。包括的尺度での評価のため、広い視点からバランスよく評価できます。
自己記入式が最も多く、視覚障害者や高齢者へ向けた面接式もあります。0~100点の範囲で得点が高いほどよい健康状態とされており、世界中で広く用いられている評価方法です。
参考:Qualitest株式会社「SF-36をはじめとする健康関連QOL尺度の提供を行っています」
SF-36®のほかには、以下の評価方法もあります。
| 評価方法 | 特徴 |
|---|---|
| EQ-5D | ・自己記入式 ・5項目の質問で構成 ・各項目3段階 |
| WHO-QOL-26 | ・自己記入式 ・WHOが開発 ・26項目の質問で構成 |
看護師が知っておきたいQOLを高める4つの視点

看護師が患者のQOLを高めるためには、自分に何ができるのかを常に意識することが大切です。疾患だけでなく、年齢・性別・生活環境・社会的立場といったあらゆる側面から患者を理解し、ケアに反映させていきます。
QOLはよりさまざまな領域に分類されますが、ここでは看護実践において特に意識したい4つの視点に絞って解説します。
身体的側面
QOLを高めるうえでの身体的側面には、以下のような項目が挙げられます。
- 疼痛緩和
- 症状コントロール
- ADL向上、機能回復
- 栄養、水分管理
- 良質な睡眠
- 感染予防
- 褥瘡や合併症の予防
疼痛や掻痒感などの身体的苦痛は、患者本人にとって一番分かりやすく、QOLを大きく下げる要因となります。そのため、日々の観察により症状を早期に把握し、必要に応じたケアや予防策を講じることが重要です。
また、患者からの訴えだけでなく、バイタルサインやスケール評価などの客観的な指標を用いたアセスメントも欠かせません。
精神的・心理的側面
精神的・心理的側面には以下のような項目があります。
- 不安の軽減
- うつ状態の緩和
- 認知機能の維持、改善
- 自尊感情や自己肯定感の維持
- 価値観や意思決定の尊重
- ストレスの緩和
- 信仰の自由の保障
精神・心理的な側面は外から見えにくい項目が多く、評価が難しい問題です。しかし、病気の治療を継続する中で湧き上がる今後の生活に対する不安は、患者のQOLを大きく下げ、生きていく気力を奪う要因となります。
特に、重度の疾患を持った患者は「なぜ自分だけが」と孤独感や無力感を抱きやすく、同時に社会的役割を失ったと感じることもあります。
こうした心の痛みに寄り添うには、まず傾聴する姿勢を持ち、信頼関係を構築していきましょう。感情や価値観を否定せず、安心して話せる環境を整えることが、心理的支援の第一歩となります。
社会的側面
QOLを高める社会的側面には、次のような要素があります。
- 人間関係の維持、再構築
- 社会や家庭における役割の継続
- 社会資源の活用支援
- 経済的な安定
先にも述べた通り、重度の疾患を持った患者は、家族や社会からのつながりが希薄になることで、それまで担っていた役割を失いやすくなります。就労の継続が困難な状態であれば、収入の減少による経済的な負担も大きくなる可能性があります。
看護師は、患者の価値観や人生における優先順位を尊重しながら、社会資源の活用の提案や助成金などの経済的な支援策にもつなげる役割があります。
環境的側面
QOLの向上には、療養環境の整備といった環境的側面も大きく関わります。以下のような視点です。
- 療養環境の快適性
- プライバシーの保護
- ICTの活用
- 自宅や施設周辺のアクセスの良さ、バリアフリーの状況
環境要因は、本人の安心感や安全性に大きく影響します。入院中であれば、ベッド周辺を清潔に保つだけでなく、温度・湿度、騒音、照明への配慮も欠かせません。
さらに退院後は、自宅環境の調整も重要です。階段や段差の有無、自宅周辺の交通環境などを多角的に評価し、必要に応じてICTを活用した健康管理やコミュニケーション手段も提案します。患者のADL に応じた住環境づくりを支援していきましょう。
患者のQOL向上のために看護師ができること

看護師は、前途の4つの側面を踏まえ、実際の看護現場でQOLを意識したケアを実施します。看護師ができることは患者のニーズによって多岐にわたりますが、ここでは5つをピックアップして解説していきます。
アセスメントで患者の想いや生活背景を深く理解する
日々のアセスメントでは、QOLに関わる情報を丁寧に収集し、看護計画へ反映させることが大切です。
バイタルサインや症状といった目に見える情報だけでなく、患者がこれまで歩んできた人生、職業歴や家庭での役割、家族構成、地域での暮らし方、価値観、目標などにも注目しましょう。
患者の考えや行動の背景にある意味を読み取る意識を持ち、観察を重ねることで、より個別性の高いケアが可能になります。
コミュニケーションを通して信頼関係を築く
患者から正確な情報を得るためには、信頼関係の構築が不可欠です。まずは患者の声に耳を傾け、気持ちに寄り添う姿勢を持つことが第一歩になります。そのうえで、価値観や人生における優先順位、治療や生活における希望などを丁寧に聴取していきましょう。
言葉だけでなく、表情やしぐさ、姿勢などの非言語的なサインにも意識を向け、プライバシーに配慮した安心して話せる環境づくりも信頼関係を築くためには必要です。
看護師に不安や想いを話せることは、患者にとっての安心感につながり、結果としてQOLの向上にも寄与します。
【関連記事】
高齢者とのコミュニケーションで看護師が意識すべき留意点は?よくある場面と対応例
その人らしさを尊重した個別ケアの実践
信頼関係が構築され、患者の価値観や希望が把握できたら、それを基に個別ケアを実践していきます。
ただし、看護師がすべてを代行することが、必ずしも患者のためになるとは限りません。必要なのは、自立を促しつつ、患者自身が意思決定し自分らしく生きる力を引き出す支援です。
たとえば、「トイレまで自分の足で歩きたい」「シャワーだけでなく湯船に浸かりたい」「趣味を続けたい」といった具体的な希望に耳を傾け、その人の生活を維持・向上できるよう、環境調整やリハビリテーションを活用していく必要があります。
快適で安心できる環境を整える
快適で安心できる環境は、患者の安眠や精神的な安定を支える大切な要素です。病室ではプライバシーを確保し、騒音や照明、室温、湿度なども細やかに配慮しましょう。
ベッド周囲の環境は、患者のADLに応じて調整します。たとえば、オーバーテーブルを使いやすい位置に配置する、頻繁に使う私物は手が届く範囲にまとめる、ポータブルトイレは適切な場所に設置するなどの工夫が求められます。
また、退院後の生活を見据えた在宅環境の整備も重要です。2階に自室がある場合は、階段昇降の負担を考慮して居室を1階に移すことを検討し、必要に応じて福祉用具の導入を専門職に相談することで、より安全で自立的な生活が可能になります。
多職種と連携し、包括的な支援を提供する
患者のQOLを高めるには、看護師一人ではなく多職種との連携が不可欠です。患者の希望に沿った最適なケアを行うためには、それぞれの専門性を活かしたチーム医療の実践が求められます。具体的には以下の内容です。
- 自宅退院を考慮した機能回復にリハビリテーションを利用する
- 自立した内服管理のための服薬指導を薬剤師に依頼する
- 訪問看護導入のために退院支援看護師に相談する
また、定期的なカンファレンスを通じて、ケアの進捗や課題、患者の変化を共有することで、チーム全体で一貫した支援を継続することができます。
QOLを意識した看護の実践例
患者のQOLを意識した看護が求められる場として、近年では在宅ケアのニーズが高まっています。ここでは、QOLを意識した看護の実践例を「病院でのケース」と「訪問看護でのケース」に分けて紹介します。
病院でのケース
病院におけるQOLを意識した看護の実践例は、以下のようなものがあります。
①「自力で排泄したい」という希望
トイレまでの移動が困難な患者の希望を尊重し、ポータブルトイレを設置。臭いの不安などの抵抗感を軽減するためにも、導入のメリットや種類を丁寧に伝える必要がある。
② 認知症によるせん妄リスク
認知症のある患者はせん妄のリスクに配慮したケアが必要です。日付や曜日がわかりやすいカレンダーの設置や、自室に目印となる張り紙を貼るなどの工夫を施す。
③ 自宅退院を目指した取り組み
退院後も自宅で安心して療養生活を続けるために、自己注射やストーマの自己管理に関する手技指導を行う。
病院では、退院後の生活を考慮し、患者が「できること」に目を向けたサポートが重要です。患者の能力を奪わずに自立を促すには、ADL向上を目的としたリハビリテーションを行う必要があります。リハビリスタッフと連携を図りながら、継続的な評価と調整を重ねていきましょう。
訪問看護でのケース
訪問看護でのQOLを重視した実践は、より生活の質に直結します。以下はその一例です。
① 「お風呂に入りたい」という希望
重度の呼吸不全がある患者の「入浴したい」という望みに対して、看護師が入浴介助を行う。
② 趣味を再開したい
趣味の庭いじりの再開を目指し、在宅酸素の使用方法の指導や、口すぼめ呼吸などの呼吸法を一緒に練習する。
③ 在宅の看取りを目指した取り組み
終末期の利用者の「最期まで家で過ごしたい」という気持ちを尊重し、疼痛緩和や環境整備を実施する。また、家族の様子にも配慮し、抱える不安を傾聴する。
在宅は医療設備が整っていないからこそ、患者の生活環境を活かした柔軟な工夫が求められます。自宅は利用者にとって最も安心できる空間です。だからこそ訪問看護師は、利用者の「したいこと」に寄り添い、その人らしい生活の継続を支える存在として、大きな役割を担っています。
また、看護師1人の視点では見落としがちな部分もあるため、事業所内のスタッフや関係職種とも連携しながら、その人の人生を支える方法をともに模索していく姿勢が大切です。
まとめ
今回は、QOLを高める看護の基本的な考えや、QOLの向上に必要な4つの視点、実践例について解説しました。
療養の場が医療機関から生活の場へと移行する中で、看護師に求められる知識や技術はますます多様化し、専門性も高まっています。
人生の質のあり方は人それぞれ異なるため、QOLを高める看護に「これが正解」という形はありません。だからこそ、患者の背景や価値観を理解し、「その人らしさをどう支えていくか」を考えながら関わることが、QOLを意識した看護の第一歩となります。
改めてQOLの本質を見つめ直し、目の前の患者が自分らしく生きられるよう支える看護を、日々の実践の中で大切にしていきましょう。
この記事をシェアする
あわせて読みたい
人気記事ランキング
ALL
週間
タグから探す
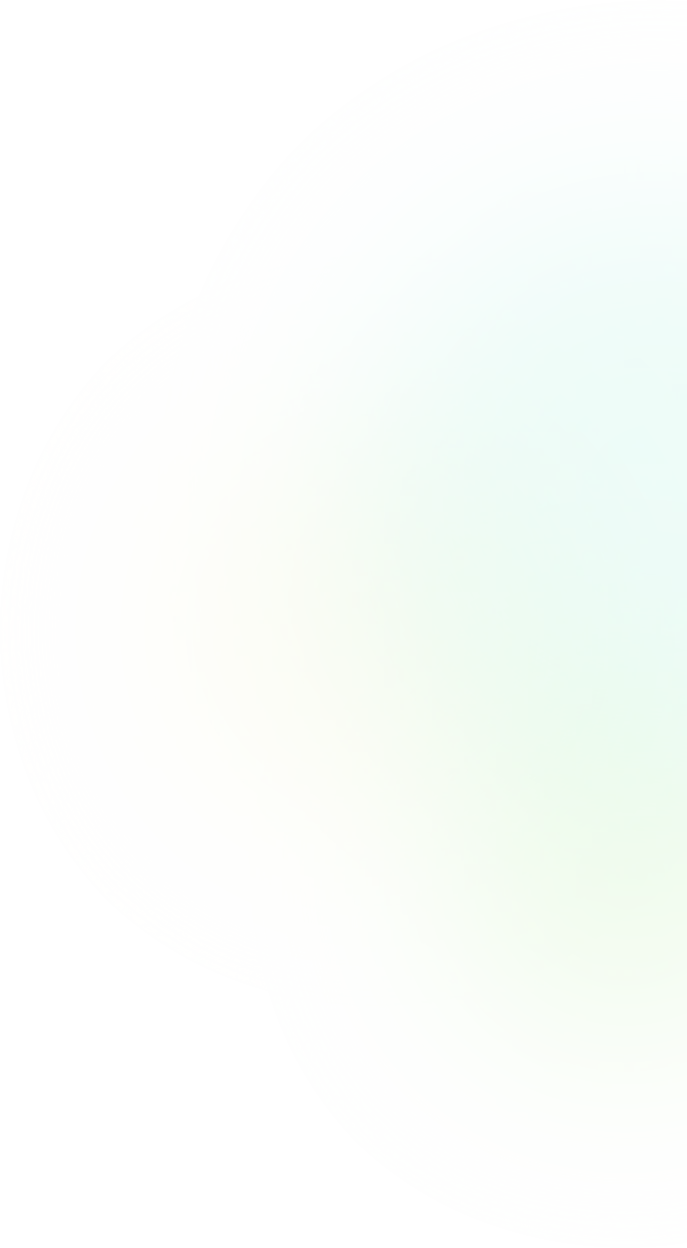
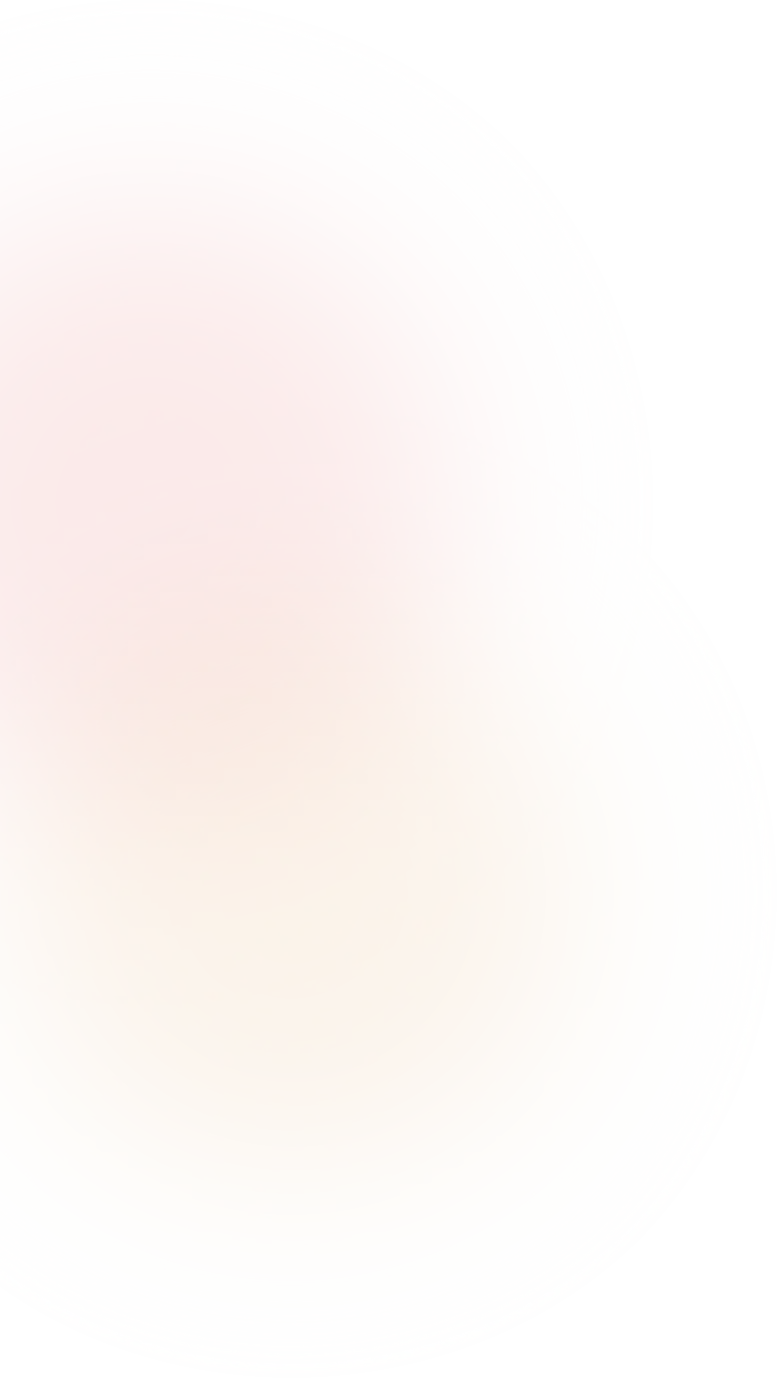












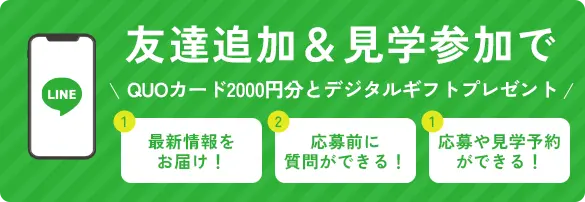


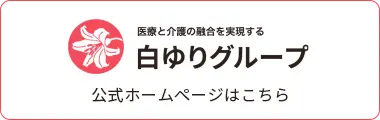
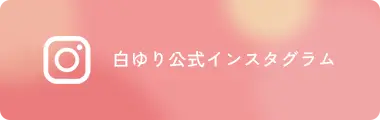
編集部
訪看オウンドメディア編集部
訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。
ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。