お悩み解決室
公開 / 最終更新
【看護師向け】夜勤明けは寝ない方がいい?疲れを長引かせない夜勤明けの過ごし方

生活リズムを崩さない対策として夜勤中に仮眠を取ることが推奨されている一方、「夜勤明けは寝ない方がいい」という話を聞いたこともあるのではないでしょうか。実際にはどうなのか気になる方もいるでしょう。
実は、夜勤明けの過ごし方に気をつけることで疲れの蓄積を防ぐことができます。
本記事では、夜勤明けの過ごし方や疲れを長引かせない工夫について解説します。自分の生活に合った方法を取り入れながら、夜勤後でも体調を整えやすい習慣づくりを目指しましょう。
2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方
目次
「夜勤明けは寝ない方がいい」は本当?

夜勤明け、帰宅後すぐに眠るべきか、それとも昼まで我慢して夜にまとめて眠るべきか 。多くの看護師が一度は悩むテーマではないかと思います。
日本看護協会のガイドラインでは、夜勤後は「短時間の仮眠で体を休め、長時間の昼寝は避ける」ことが推奨されています。これは、長く眠りすぎることで体内時計がさらにずれてしまい、夜間の入眠が難しくなってしまうためです。
つまり、「夜勤明けは寝ない方がいい」というより、「長時間は寝ない方がいい」が正しいと言えます。
参考:日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
生活リズムの乱れが心身に与える影響
人には日中に活動し夜に眠るという体内リズムがありますが、夜勤はこのリズムを逆転させるため、心身に大きな負担を与えます。
体内時計が乱れることで睡眠の質が低下し、慢性的な疲労や集中力の低下を感じやすくなります。
さらに、夜勤を続けていくことでおのずと不規則な生活が続くと、自律神経やホルモンバランスが乱れ、免疫力の低下も招くおそれもあります。
こうした影響は蓄積しやすく、体調不良やモチベーション低下につながるため、夜勤後に疲れを感じやすい方は休み方を工夫することが重要です。
2交代制と3交代制の違い
夜勤明けの過ごし方は、勤務体制によっても異なります。
2交代制では夜勤の拘束時間が長く心身の負担が大きいものの、明けの翌日が休みになることが多く、まとまった休息を取りやすいのが特徴です。
一方、3交代制は準夜勤・深夜勤に分かれており、夜勤の頻度が多くなる傾向があります。そのため、短時間でも質の高い睡眠を確保する工夫が必要になります。
このように同じ夜勤明けでも、勤務体制によって適切な過ごし方は異なります。
なぜ夜勤明けにしっかり寝ても疲れが残るのか
夜勤明けに「たっぷり寝たはずなのにスッキリしない」と感じるのは、主に睡眠の質と自律神経の乱れが関係しています。
日中は、身体が「活動モード」に切り替わっている時間帯なので、光や音の影響を受けやすく、深い眠りに入りにくいとされています。その結果、昼間に長時間眠っても脳や身体が十分に回復できません。
つまり、眠る時間が長ければ長いほど疲れが取れるというわけではなく、「どれだけ質の良い睡眠を取るか」が疲労回復のポイントになります。
夜勤明けの看護師におすすめの仮眠時間の目安は?
夜勤明けの仮眠時間は、およそ2時間程度が望ましいとされています。このくらいの時間であれば深い睡眠に入りすぎず、脳と身体の疲労回復にも効果的です。
仮眠後はカーテンを開けて太陽光を浴び、できるだけ普段通りの生活を送るようにしましょう。夜は早めに就寝することで体内時計がリセットされ、疲労の回復にもつながります。
夜勤明けに質の高い睡眠をとるための準備方法

夜勤明けに「とりあえず寝る」だけでは十分に疲れが取れないこともあります。体内リズムが乱れた状態では眠りが浅くなりやすいため、限られた睡眠時間でもしっかり回復できるよう睡眠の質を高める準備が大切です。
ここでは快適な睡眠環境の整え方や入眠前の工夫について紹介します。
快適な睡眠環境を整える
夜勤明けにしっかり疲れを取るためには、睡眠環境を整えることが欠かせません。以下のリストを参考に、睡眠環境を整えてみてください。
- 光を遮るために遮光カーテンやアイマスクを使用する
- 静かな環境を確保し、音の刺激を最小限にする(耳栓を使うのもあり)
- 室温は20~26℃、湿度は40~60%を目安に調整する
- リラックスできる寝具やパジャマを選ぶ
病院から自宅へ帰るまでの間も帽子やサングラスなどで太陽光を遮ることで、脳の覚醒を防ぐ効果があります
軽めの食事を取る
夜勤明けにお腹が空いて眠れないときは、無理に我慢せず、消化に優しい軽食を取るのも一つの方法です。
みそ汁やスープなどの温かい汁物はリラックス効果があり、睡眠前の食事に適しています。また、おにぎりやうどんといった消化の良い炭水化物もおすすめ。
逆に、脂っこい食事やカフェインを含む飲料は、入眠を妨げる原因になるため避けましょう。
眠れないときはぬるめのお風呂でリラックス
疲れているのに眠れないと感じるときは、ぬるめ(38~40℃)のお風呂に軽く浸かるのも効果的です。身体を温めることで副交感神経が優位になり、心身がリラックスして眠りに入りやすくなります。
ただし、熱すぎるお湯や長時間の入浴は逆効果になることもあるため、適度な温度と時間を意識しましょう。
夜勤明けの過ごし方|3パターン
夜勤明けの過ごし方は、体調に合わせて工夫することが大切です。ここでは、看護師が実践しやすい3つの過ごし方を紹介します。
それぞれのメリットや注意点も解説するので、自分に合った方法を見つけ、疲労を翌日に持ち越さない工夫として参考にしてみてください。
仮眠をとってから午後に行動するパターン
午前中に仮眠をとり午後から活動するパターンは、疲労回復と生活リズムの維持の両立に最も適しています。
目安として午前中に2時間程度の仮眠をとることで、身体の疲れが軽減され、午後からの活動に支障が出にくくなります。また、日中の時間を有効に使えるため、買い物や家庭の用事、趣味の時間にも充てやすい点がメリットです。
ただし、仮眠を長く取りすぎると夜間の睡眠リズムが乱れるおそれがあるため、時間と質のバランスを意識しましょう。
快適な睡眠環境の整備や軽めの食事を取るなど、仮眠前の工夫も合わせて行うと疲労回復により効果的です。
寝ずにそのまま1日を過ごすパターン
仮眠をとらずにそのまま活動するパターンは、自由時間を長く確保できるのが特徴です。
家事や買い物などに多くの時間を使える反面、体力の消耗や集中力の低下につながる可能性もあります。そうしたリスクも考慮しつつ、自分の体調や疲労度に応じて無理のない過ごし方を選ぶことが大切です。
夜は早めに就寝し、十分な睡眠を確保して翌朝に疲労を残さないようにしましょう。
また、軽めの食事やぬるめの入浴など、夜間の入眠をスムーズにする工夫を取り入れると、翌日の体調管理に役立ちます。
夜勤明けに準夜勤が続くパターン
夜勤明けの翌日に準夜勤が控えている場合は、体内リズムを極力崩さないことが重要です。
無理に昼過ぎまで起きていると体内時計が乱れやすくなり、次の勤務に影響が出ることもあります。帰宅後はなるべく早めに仮眠をとり、短時間でも深く眠れるようカーテンを閉める・静かな空間をつくるなど工夫を行いましょう。
体をしっかり休めることで、次の準夜勤にも集中して取り組みやすくなります。
夜勤明けに避けたいNG行動
ここでは、夜勤明けに避けたい睡眠の質を下げやすい行動について解説します。
カフェインやアルコールの摂取
夜勤明けにカフェインを摂ると一時的に目が覚めやすくなりますが、睡眠の質を低下させるため、仮眠の妨げになります。
また、アルコールはリラックス効果があるように感じられますが、同じく睡眠の妨げになるため疲労回復の効果を低下させる要因になりかねません。
どうしても摂取したい場合は、仮眠の後などに時間をずらし、できる限り控えるのが望ましいでしょう。
スマートフォンの見過ぎ
スマートフォンやタブレットの画面から発せられるブルーライトは、体内時計を乱す要因となります。
特に仮眠前や就寝前に長時間操作すると、入眠しにくくなり、眠りも浅くなるため注意が必要です。できれば仮眠前のデジタル機器の使用は控えましょう。
予定を詰め込みすぎる
「せっかくの時間を有効に使いたい」と、夜勤明けに予定を詰め込んでしまう方もいますが、疲労が抜けきっていない状態では身体に負担がかかりやすくなります。
無理のないスケジュールを心がけ、まずは身体をしっかり休めることを優先しましょう。
夜勤疲れを長引かせない過ごし方のコツ

夜勤後の疲れを長引かせないためには、生活リズムを整えつつ、質の高い睡眠と適度な休息を確保することが重要です。
以下に、疲労を溜め込まないための過ごし方のコツを紹介します。
軽い運動やストレッチを日常に取り入れる
夜勤明けや日中の疲労を軽減するためには、軽い運動やストレッチが有効です。適度な運動は、血流が促進し、体内の老廃物や疲労物質の排出を助け、疲労回復を早める効果が期待できます。
また、ストレッチで筋肉の緊張を和らげることで、肩こりや腰痛などの身体的ストレスを軽減することも可能です。
無理のない範囲で身体を動かすことは心のリフレッシュにもつながり、夜勤による生活リズムの乱れや倦怠感の緩和にも役立ちます。
バランスのとれた食事を心がける
夜勤明けの疲労回復や体調維持には、日頃からバランスのとれた食事が欠かせません。
主食・主菜・副菜を組み合わせ、タンパク質・炭水化物・脂質のほか、ビタミンやミネラル、食物繊維も意識して摂取することが大切です。栄養バランスのとれた食事はエネルギー不足や免疫力低下を防ぎ、体調の安定につながります。
ただし、夜勤明けは無理に食べすぎず、消化に良い食事を意識しましょう。
どうしてもつらいときは無理せず休む
夜勤明けに体調がすぐれない・強い疲労を感じるときは、「寝ない方がいい」と思いこまず、しっかり休むことも大切です。
無理に起きて活動すると、かえって疲れが蓄積し、生活リズムの乱れにもつながります。疲れを感じたときは思い切って長めに休息をとることで回復が早まり、翌日の勤務や日常生活の影響も少なくなります。
自身の体調と相談し、柔軟に仮眠時間を調整することが、夜勤と上手に付き合っていくためのポイントです。
夜勤がつらい場合は転職も視野に入れる
夜勤明けの疲労が強く、生活リズムの乱れや体調不良が続くようであれば、無理をせず転職という選択肢も検討してみましょう。
夜勤のない職場であれば、生活リズムも整いやすくなります。例えば、訪問看護やクリニックなどでは日勤のみの働き方が可能な場合も多く、家庭やプライベートとの両立を重視する方に向いています。
また、転職を考える際には、職場の雰囲気や業務内容を事前に知るために、見学会への参加がおすすめです。実際の働く環境を自分の目で確認することで、安心して新しい一歩を踏み出すことができます。
「今のまま働き続けて大丈夫だろうか」と感じたときは、自分の心身と向き合い、より自分らしく働ける環境を探すことも大切です。
【関連記事】
夜勤を辞めたい…原因と対処法は?日勤で働ける転職先も紹介
まとめ
夜勤明けは、仮眠時間や睡眠環境を工夫することで、疲労を効率的に回復させることができます。
光や食事、軽い運動などを取り入れて生活リズムを整えながら、体調に応じてしっかり休息をとることが健康維持のポイントです。
もし夜勤の負担が大きいと感じる場合は、夜勤のない職場への転職も前向きな選択肢として検討してみましょう。自分の体を大切にしながら、無理なく働ける方法を選ぶことが、長く看護の仕事を続けるための第一歩です。
参考:日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
この記事をシェアする
あわせて読みたい
人気記事ランキング
ALL
週間
タグから探す
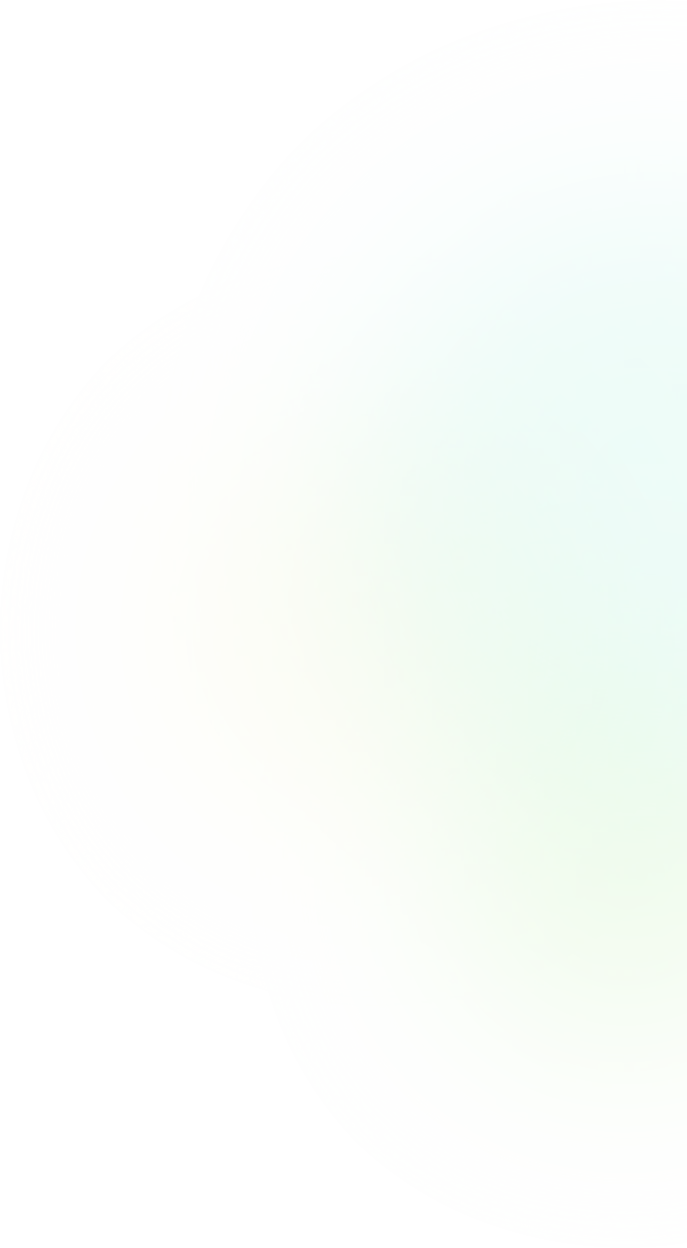
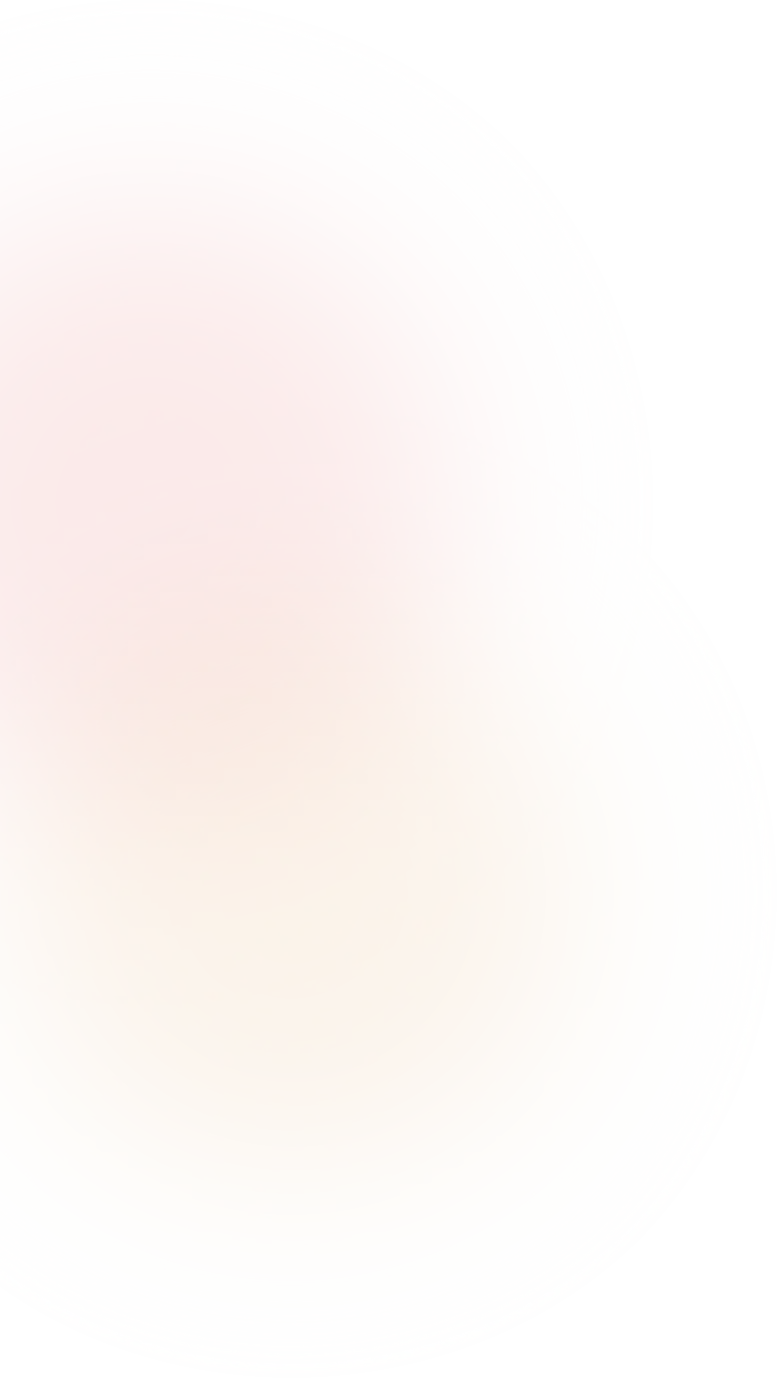












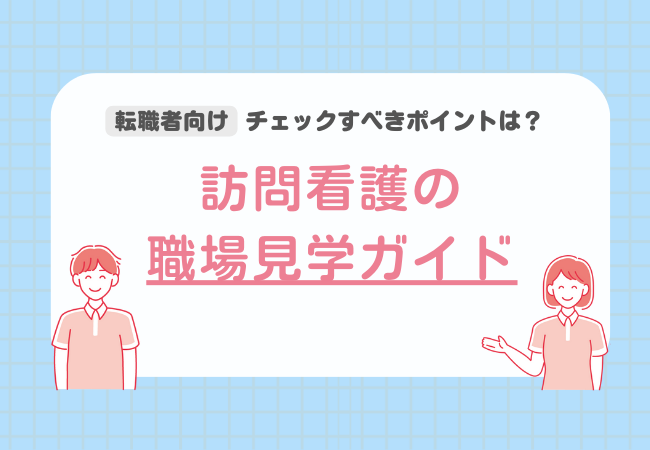



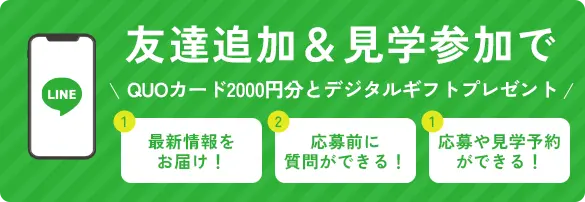


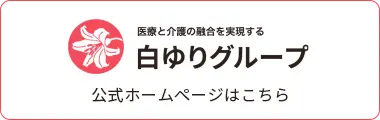
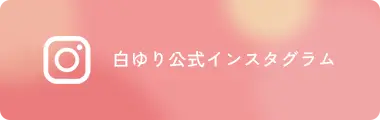
編集部
訪看オウンドメディア編集部
訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。
ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。