お悩み解決室
公開 / 最終更新
看護における傾聴の姿勢とは?実践方法・高めるスキルまで解説

看護の現場では「傾聴」の重要性が語られますが、具体的な方法や効果について詳しく知らない方も多いかもしれません。
看護における傾聴は単に耳で「聞く」のではなく、患者の言葉の背景にある気持ちや考えを理解するためのコミュニケーション技術です。適切な傾聴により、患者との信頼関係の構築や適切なケアの提供につながります。
本記事では、看護師が知っておきたい傾聴の基本的な姿勢や具体的な実践方法を解説します。
2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方
目次
傾聴は「耳・目・心」で聴くコミュニケーションのこと

傾聴とは、耳で聞き、目で相手を見て、心を傾けながら相手の話に寄り添うことです。
傾聴とは、相手に関心をもって、相手の話に注意深く耳を傾けることである。それは、相手が何を伝えようとしているのか、何を伝えていないのかを聴きとりながら、相手の自己表出を促していく行為である。
引用:日本看護科学学会. 看護学学術用語検討委員会. n.d. JANSpedia-看護学を構成する重要な用語集-. 傾聴.
https://www.jans.or.jp/glossary/listening/ (2025年11月12日閲覧)
日本看護科学学会では、傾聴をこのように定義しており、信頼関係を築く上で重要な行為としています。傾聴には、言葉や表情、態度を通して伝えようとしていることを理解しようとする姿勢が求められることがわかります。
看護現場における傾聴の目的と重要性
看護現場における傾聴の目的は主に2つあり、
1つ目は患者との信頼関係を築くこと、2つ目は患者の真のニーズを理解することです。
信頼関係の土台が築かれることで、患者一人一人に合った適切なケアへとつながります。傾聴はその基盤をつくる、非常に重要な役割を担っています。
看護師の傾聴がもたらす3つの効果
傾聴により、以下の3つの効果が期待できます。
- 信頼関係の構築
- 患者は「自分の話を理解してもらえている」と感じやすくなり、看護師への信頼が高まります。信頼関係が築かれることで、悩みや不安を話してもらいやすくなり、ニーズの把握にも効果的。
- 安心感の提供
- 不安や痛みを抱える患者にとって、話を真剣に聴いてもらえることは大きな安心につながり、治療への前向きな姿勢や回復力の向上にも良い影響を与えます。
- 自己理解と自己受容の促進
- 思いを言葉にする過程で気持ちが整理され、状況を客観視しやすくなります。患者の自己理解が深まり、現状の受け入れや前向きな対処につながることがあります。
傾聴を構成する3つの要素|ロジャーズの3原則
傾聴の基本となる考え方として、心理学者のカール・ロジャーズが提唱した3つの原則があります。
共感的理解
共感的理解とは、相手の考えや気持ち、立場などに共感し、理解しようとする姿勢です。
これは単に「わかります」と言うだけでなく、相手の感じている世界を相手の視点から理解しようとする積極的な試みを意味します。
たとえ自分とは考え方が異なっていても、まずは患者の立場で受け止め、どのように感じ、考えているかを理解しようとすることで共感を示します。
無条件の肯定的関心
無条件の肯定的関心とは、相手の話を善悪などで評価せずに聴く姿勢のことです。
患者の話の内容に対して、「それは良くない考えだ」「そんなことを考えるべきではない」などと判断せず、背景にある気持ちに肯定的な関心を持って聴くことが重要としています。
この姿勢によって、患者は自分の考えや感情を否定されることなく安心して話すことができ、自己開示が促進されるのです。
自己一致
自己一致とは、看護師が感じていることと、話し手の言葉や態度が一致していることを指します。
わからないことをわかったふりをしたり、共感できないことに無理に共感を示したりするのではなく、自分の感情や考えに正直であることが重要です。
例えば、患者の話の内容が理解できない場合は、「すみません、よく理解できませんでした。もう一度教えていただけますか?」と素直に伝えるようにします。
このように相手にも自分にも誠実な態度により、信頼関係の構築を目指します。
傾聴における3つの実践方法
傾聴には、受動的傾聴・反映的傾聴・積極的傾聴の3種類の実践方法があります。状況や目的に応じて方法を使い分けましょう。
受動的傾聴
受動的傾聴は、聞き手として相手の話を最後まで聞き、受け止めるという傾聴の基本です。
この方法は、相手の話を肯定的に聞くことに徹底するため、話を受け入れられていると感じてもらいやすく、気持ちを吐き出してもらう場面などに効果的とされています。
具体的には、「はい」「そうですね」などの相槌を適切なタイミングで入れながら最後まで相手の話に集中し、聞く最中は自分の意見を挟まないことです。
相手のために聴くという姿勢が大切で、正面を向いて目線を合わせる・うなずくなど、非言語コミュニケーションも重要な要素となります。慣れないうちは、聞ききることに集中してみましょう。
反映的傾聴
反映的傾聴は、相手の話す内容を自分なりの言葉で繰り返すことで、共感や理解を示す方法です。
相手の言葉を繰り返す・言い換える・要約することで、「あなたの話をしっかり聞いていますよ」というメッセージを伝えます。
例えば、患者が「夜になると痛みがひどくなって眠れないんです」と言った場合、「夜になると痛みが強くなって、眠れなくなってしまうのですね」と返すことで、相手の言葉を受け止めていることを示します。
しかし、都度確認の言葉を返したり、返答の内容によっては誤解を招く可能性もあるため、適切な場面での使用が求められる点には注意が必要です。
この方法により、患者は自分の話を理解してもらえていると感じやすく、看護師としても感情や状況のすり合わせができ、共感が深まります。
積極的傾聴
積極的傾聴は、相手の話に主体的な働きかけをし、考えに対する理解を促す方法です。受動的傾聴や反映的傾聴よりもさらに一歩踏み込んだコミュニケーションとなります。
具体的には、「それについてもう少し詳しく教えていただけますか?」といった質問をしたり、「そのとき、どのようなお気持ちでしたか?」と感情に焦点を当てた問いかけをしたりします。
また、「今おっしゃったことから、〇〇ということが大切なのですね」といった気づきを伝えることもあります。
ただし、適切なタイミングで行わなければ話を遮ってしまう可能性もあるため、タイミングを見極め、ケースバイケースで活用する必要があります。
高度なテクニックですが話し手の思考を促すという点でも有効なので、より円滑なコミュニケーションの実現に役立つでしょう。
看護師が身につけたい傾聴時の「姿勢」

傾聴は言葉だけでなく、聞く際の「姿勢」も重要です。
患者は、看護師の表情、視線、体の向きなどの非言語的な要素からも安心感や信頼感を得ています。これらは非言語的コミュニケーション(ノンバーバルコミュニケーション)と呼ばれ、効果的な傾聴には欠かせない要素です。
アイコンタクトと目線の高さ
アイコンタクトと目線の高さは、相手の話に関心があることを示す重要な手段です。
【アイコンタクト】
視線をそらさず、相手の目を見て話すことで「話をしっかり聞いていますよ」というメッセージを伝えることができます。
❗見つめすぎると相手に緊張や不安を与えてしまうことがあるため、会話の途中で自然に目線をそらしたり、メモを取ったりするなど、適度なアイコンタクトを心がけましょう。
【目線の高さ】
可能な限り患者と同じ目線の高さでコミュニケーションを取りましょう。しゃがむ、座るなどで目線の高さを合わせるよう意識してみてください。
❗座っている患者に対して立ったままでいると、威圧感を与えたり、距離を感じさせたりすることがあります。
話を遮らず、うなずきや相槌を使う
患者が話している途中で口を挟んだり、言葉を遮ったりすることは傾聴の妨げになります。特に高齢の患者は言葉を選びながらゆっくり話すことが多いので、途中で話を遮らないよう注意が必要です。
「そうなんですか」「なるほど」「私もそう思います」などの相槌を適度に挟むことで、相手の話に関心を持って聴いていることを伝えることができます。
声のトーンを意識し、しつこくない程度にうなずくことも重要です。相槌やうなずきは、患者の話のペースを尊重しながら、適切なタイミングで行うことを意識しましょう。
【関連記事】
高齢者とのコミュニケーションで看護師が意識すべき留意点は?よくある場面と対応例
興味・関心を示す表情づくり
どんなに丁寧な言葉遣いをしていても、無表情や疲れた表情では相手に関心がないと伝わるおそれがあります。穏やかで柔らかい表情を心がけることで、相手に安心感を与え、話しやすい雰囲気をつくることができます。
また、相手の感情に合わせて表情を変える「ミラーリング」も効果的です。
例えば、患者が笑っているときに自分も微笑むなど、相手の感情を自分の表情に映すことで共感の気持ちを伝えることができます。
表情は無意識のうちに出てしまうものですが、意識的に表情をコントロールすることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
時には沈黙も受け止める
傾聴の中で、患者が沈黙する場面もあります。そんなときは焦って会話を広げようとせず、その沈黙を「相手が気持ちを整理する時間」として受け止めることも必要です。
待つことで相手から自然と言葉が出てくることもあるため、沈黙の間も表情や視線の意識は途切れさせず、いつでも話を聴ける姿勢を示すことが重要になります。
沈黙を受け止めることを会話が弾まないとマイナスに考えるのではなく、相手のペースを尊重し、話しやすい空気感をつくる間であると捉えることで、より効果的なコミュニケーションになりえます。
看護師におすすめ!傾聴の具体的なスキル
ここからは、傾聴の効果をさらに高めるための具体的なテクニックを紹介します。これらのスキルを身につけることで、より質の高い傾聴が可能になります。
聴く8割・話す2割を意識する
効果的な傾聴は、看護師が話す時間よりも患者が話す時間の方が長くなるのが理想的です。目安として、聴く8割、話す2割の割合を意識しましょう。
患者が話しているときは基本的に聴く姿勢に徹し、考えたり言葉に詰まったりする様子があれば、そっと言葉を添える程度にとどめることが大切です。
自分が話しすぎていないか時々振り返ることで、患者中心のコミュニケーションが可能になります。
バックトラッキング
バックトラッキングとは、オウム返しのように相手の話を繰り返す技法です。
「〇〇だったんですね」など、相手の言葉を一部真似る返答により、相手の話に関心を持っていることを伝えます。これは、前述した反射的傾聴に含まれるスキルです。
バックトラッキングは、相手の感情や考えを理解する手助けになるとともに、相手の自己表現を促進する効果もあります。
ただし、多用したりタイミングを間違えたりすると不自然に感じられるため、相手の反応を確認しながら活用しましょう。
ペーシング
ペーシングとは、相手の話す速度や声の大きさ、トーン、相槌などを合わせることです。話し手と同じペースでコミュニケーションを取ることで安心感を与えるだけでなく、より共感しやすくなります。
例えば、ゆっくり話す患者にはゆっくりと応答し、活発に話す患者には元気よく応答するなど、相手のコミュニケーションスタイルに合わせることが大切です。
ただし、無理に合わせるとわざとらしくなるため、自然に合わせられる範囲で行うことがポイントです。
ペーシングにより、相手との間に心理的な距離が縮まり、より深いコミュニケーションが可能になります。
オープンクエスチョンの活用
オープンクエスチョンとは、「はい」「いいえ」では答えられない、自由な回答を促す質問方法です。オープンクエスチョンを織り交ぜた質問方法は、患者が自由に気持ちを話しやすくするのに効果的です。
5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を用いた質問により、患者は具体的に自分の状況や気持ちを表現することができます。
例えば、「痛みはどのようなときに強くなりますか?」「どのように感じていますか?」といった質問です。
オープンクエスチョンを活用することで、患者の状況をより深く把握できるだけでなく、相手に考えを深めてもらう効果も期待できます。
日常的に傾聴を実践し、傾聴力を高めよう
傾聴は一朝一夕で身につくものではなく、日々の看護実践の中で意識的に取り入れ、少しずつ磨いていくスキルです。
すべてのテクニックを一度に試すと不自然なコミュニケーションになりかねないため、「今日は目線の高さを意識する」など、自分にできそうなものから始めるのがおすすめ。また、先輩看護師の傾聴の姿勢を観察するのも有効です。
実践したスキルを振り返りながら、自分に合った傾聴のスタイルを見つけていきましょう。
コラム|訪問看護における傾聴は背景理解がカギ

訪問看護では病院とは異なる環境でケアを行うため、生活環境や家族関係、地域とのつながりなどを含む広い視点が不可欠です。
「なぜそのように考えるのだろう?」と常に想像を働かせ、言葉の背景にある想いに耳を傾けます。
「薬を飲みたくない」という訴えは、単に指示に従わないと捉えるのではなく、「過去に副作用があったのか」「経済的な理由があるのか」など、多様な背景が潜んでいるかもしれません。
言葉だけでなく生活環境や表情、家族との関係性などを総合的に捉えることで、その人が望む療養生活の実現や自立を促すことができます。
在宅において丁寧な傾聴と背景理解こそが、信頼関係を築き、その人らしい生活を支える鍵になるのです。
以下に、訪問看護の信頼関係についてエピソードを交えたインタビュー記事を掲載しています。
👉大切なのは信頼関係という下地。看護師が語る訪問看護の奥深さ
まとめ
本記事では、看護における傾聴の目的や重要性、具体的な実践方法を解説しました。
傾聴は、耳・目・心を使って相手の言葉の奥にある思いを理解しようとする姿勢です。看護現場では、患者との信頼関係を築き、適切なケアを提供するための基本スキルとなります。
アイコンタクトや相槌、表情なども意識しながら実施することで、傾聴の質を高めることができるでしょう。
また、傾聴力はすぐに身につくものではなく、日々の看護実践の中で意識的に取り入れながら少しずつスキルを高めていくことが重要です。
患者の言葉に真摯に耳を傾けながら、より質の高い看護の提供につなげていきましょう。
この記事をシェアする
あわせて読みたい
人気記事ランキング
ALL
週間
タグから探す
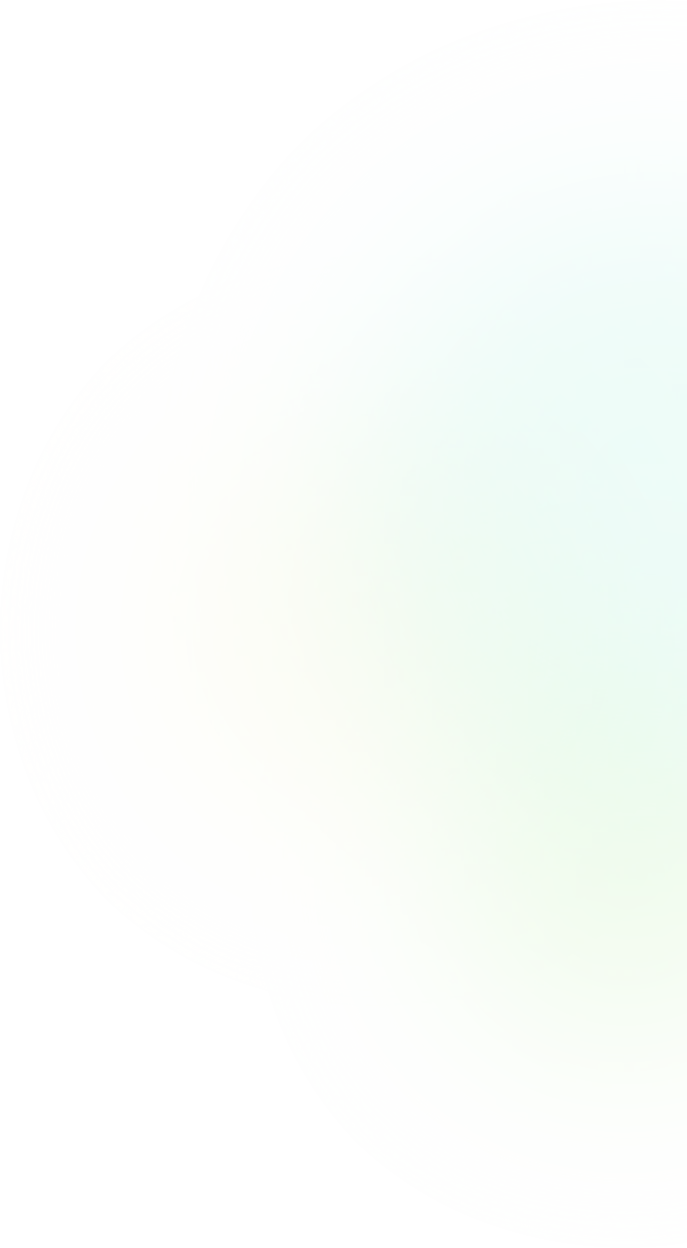
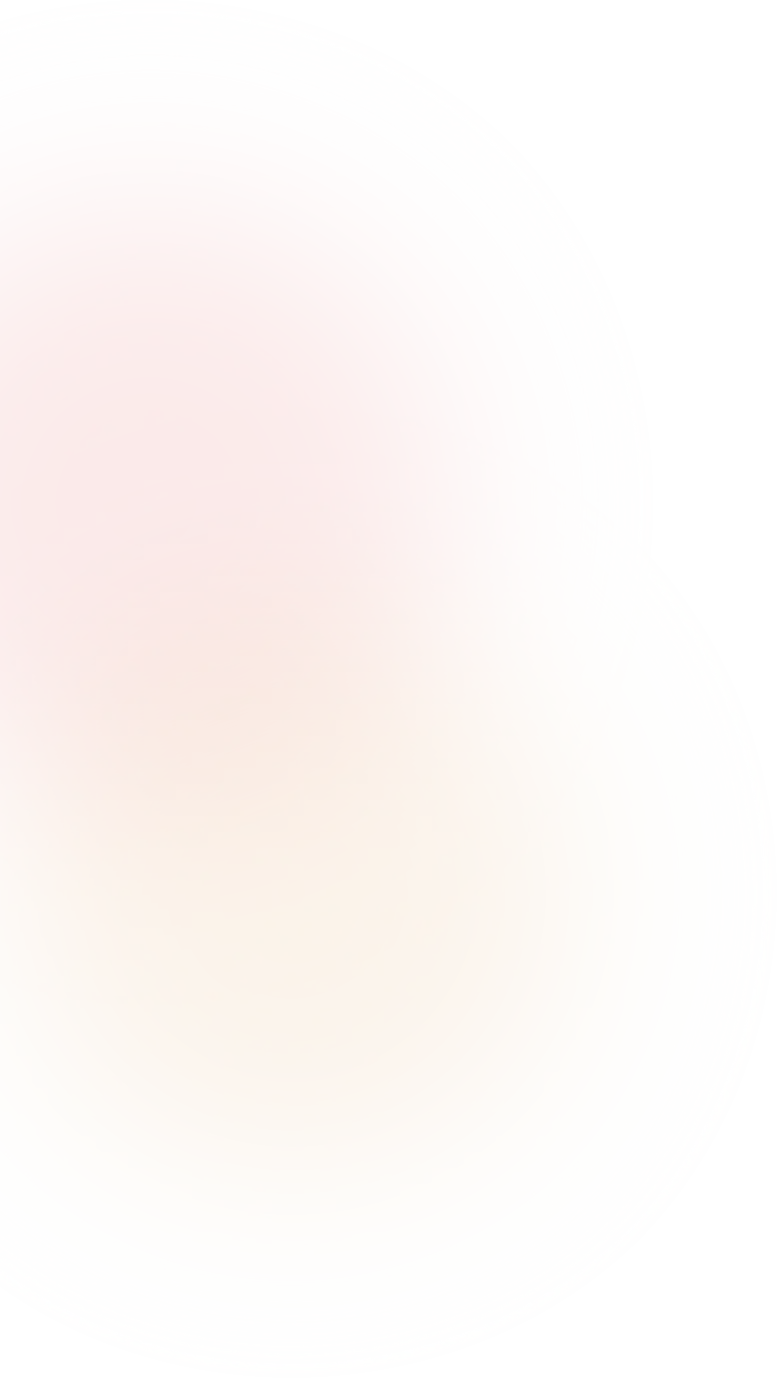
















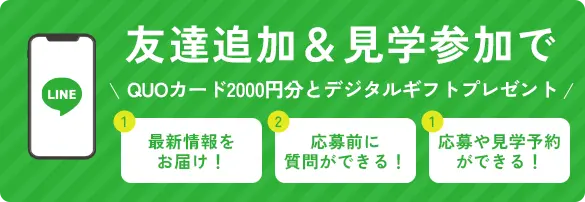


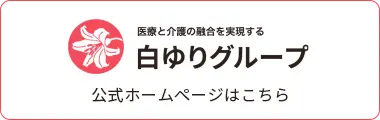
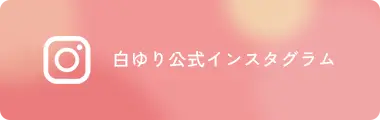
編集部
訪看オウンドメディア編集部
訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。
ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。