お悩み解決室
公開 / 最終更新
もう迷わない!看護に必要なコミュニケーションとは?患者・看護師同士で大切なポイントやスキルアップの方法

看護師という職業は、日々の多忙な業務をこなすと同時に、患者への理解を深めて医療と患者をつなぐという大切な役割があるため、患者とのコミュニケーションが看護の質を左右します。
また、患者だけではなく、同僚や多職種との連携にもコミュニケーションは不可欠です。
この記事では、看護の現場で活用できるコミュニケーションの方法や、患者やスタッフとのコミュニケーションを円滑に進めるポイントについて解説します。コミュニケーションが苦手に感じている看護師の方は、ぜひ参考にしてください。
2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方
目次
看護師にコミュニケーションスキルが必要な理由
看護師にコミュニケーションスキルが必要な理由は多岐にわたりますが、基本的には患者との信頼関係の構築・医療チームと連携する場面で重要なスキルとなります。
| 必要な理由 | 理由の重要性 |
| 患者との信頼関係構築 | 患者の背景を尊重したコミュニケーションが取りやすくなることで、患者の状態を正確に把握でき、適切なケアの提供やセルフケア指導が可能。 患者が安心して治療を受けやすくなる。 |
| 医療チームとの連携 | 医師や看護師、多職種との連携をスムーズにすることで、質の高い医療の提供が可能。 |
看護師のコミュニケーションスキルは単なる情報伝達の手段ではなく、患者のQOL向上や医療の質向上にも大きな役割を果たします。
患者とのコミュニケーションのポイント

看護師が患者とコミュニケーションを取るうえで重要なことは、安心感を与えながら信頼関係を築くことです。患者とのコミュニケーションで大切にするべきポイントは下記の通りとなります。
・会話の基本は傾聴
・相手の立場になって共感する
・客観的な視点を持つ
・表情や態度を意識する
・感情をコントロールする
それぞれ詳しく説明します。
会話の基本は傾聴
傾聴とは、相手の話に関心を持ち、共感的な姿勢で注意深く「聴く」ことを指します。相手に「自分の話が大切にされている」という感覚を持ってもらいやすく、信頼関係を築くための大切なスキルです。
・相手の話を遮らずに最後まで話しを聞く
・相手の話や感情を否定しない
・自分の考えを押し付けない
上記のような意識で話を聞くことにより、患者の気持ちや意図を深く理解しようという姿勢が相手に伝わりやすくなります。声のトーンや表情からも相手の感情を感じ取れるように、細かく観察することも重要です。
相手の立場になって共感する
単に相手の話を聞くのではなく、相手の気持ちや状況を自分がその場にいるような感覚で理解しようと努めることが「共感」です。相手が何を考え、何に困り、何を感じているのかを想像し、感情に寄り添う姿勢が大切となります。
例えば「それは大変でしたね」などといった言葉で相手の感情を受け止め、さらに「それでどうしたんですか?」と心情を引き出す質問をすると、患者は「この人は自分の話に興味を持ってくれている、話してみようかな」という前向きな気持ちになりやすいでしょう。
客観的な視点を持つ
コミュニケーションにおいて客観的な視点を持つことは、感情や個人的な価値観に左右されず、公正な立場から情報や意見を伝えたり受け取ったりすることを意味します。
患者の訴えや状態を客観的に捉えながらアセスメントをすることで、誤解や感情的な対立を避け、建設的な対話が可能になります。
表情や態度を意識する
コミュニケーションは言葉だけでなく、態度や表情からも相手の感情や考えを読み取ることができます。
看護の現場でも患者に安心してもらう目的で、視線の高さを合わせて会話する・頷きや相槌を適度に挟む・柔らかい笑顔で接するといった、非言語的コミュニケーションを実施する場面があります。
相手の表情・声のトーン・話し方・姿勢や動作などを観察しながら「どういった状態か」を読み取り、ことで、気持ちに寄り添った会話が可能です。これをキャリブレーションといいます。
感情をコントロールする
看護は人を相手にする仕事なので、焦りや怒り、悲しみといった負の感情に揺れ動くこともありますが、看護師には負の感情をなるべく表に出さないように感情をコントロールすることが求められます。
自分の感情を客観的に捉え、感情が高ぶる場面では深呼吸をしながら感情をコントロールし、患者とのコミュニケーションを円滑に進められるように努めます。
また、完璧を求めすぎずに適度に受け流すことも大切です。毎日少しでも自分がリラックスできる時間を確保し、疲れやストレスを溜めすぎないようにしましょう。
患者とのコミュニケーションにおいては、タッチングを用いるのも効果的です。以下の記事で詳しく説明しています。
【関連記事】
看護におけるタッチングの効果は?具体的な実践方法も紹介
看護師同士でのコミュニケーションのポイント

看護師同士で円滑なコミュニケーションが取れると、仕事のストレスも軽減し、チームとしての連携が強まります。多忙な業務のなかでより良い看護を提供するためには、効率的にコミュニケーションを取り、迅速かつ正確な情報共有が不可欠です。ここでは下記3点のポイントについて説明します。
・情報共有は「PREP法」で結論から伝える
・5W1Hを押さえた報告・連絡・相談(報連相)を意識
・看護師同士の協調性を大切にする
情報共有は「PREP法」で結論から伝える
要件を簡潔で分かりやすく相手に伝える方法に、PREP法というものがあります。PREP方は、「結論」「理由」「具体例」「結論」で構成され、あらゆるビジネスシーンで使われているフレームワークです。
【看護現場における報告の例】
| Point(結論) | Aさんが発熱。38.5℃です。何らかの対応が必要な状態です |
| Reason(理由) | 今朝から咳がひどくなり、食欲も落ちています |
| Example(具体例) | 血圧は安定していますが、少し倦怠感を訴えています |
| Point(再確認) | 医師に報告し、対応を確認します |
このように、まず結論から述べることで、どういった内容の報告なのかを理解してもらいます。さらに結論の理由や背景を説明し、最後に再度結論を伝えることで、相手が状況を把握しやすくなるでしょう。
5W1Hを押さえた報告・連絡・相談(報連相)を意識
看護の現場において、チーム間での情報共有は非常に重要です。そのため、報告・連絡・相談は的確かつこまめに行う必要があります。
代表的なフレームワークとして、いつ(When)、どこで(Where)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)を整理して伝える5W1Hという方法があります。
相手に伝えたい情報をある程度整理して説明しやすくなるため、コミュニケーションが苦手な方はまず、5W1Hを意識してみましょう。
【看護の現場における報告の例】
| いつ(When) | 本日14時から |
| どこで(Where) | Aさんの病室で |
| 誰が(Who) | B医師の指示で |
| 何を(What) | Aさんの点滴が〇から△に変更になった |
| なぜ(Why) | 血糖値が上がりすぎたため、ブドウ糖濃度を下げる目的 |
| どのように(How) | 旧点滴終了後、新しい点滴を接続する |
情報の共有と引継ぎが的確にできるよう、事実を客観的に述べることを意識します。
看護師同士の協調性を大切にする
看護師にはチームワークが求められるため、自分の業務を把握しながらもチームメンバーとの連携を図る必要があります。
例えば、相手の意見を尊重する・状況に合わせて適切な行動を選択する・意見の違いも対話で解決できるよう努める・チーム全体の利益を考えて行動するといった姿勢を意識することで、チーム全体のまとまりがよくなります。
現場で起こるミスは、チーム内におけるコミュニケーション不足が影響する場面もあるため、「チーム」を意識しながら情報共有をするようにしましょう。
コミュニケーションスキルがアップする具体的な方法

コミュニケーションにおいて大切にすべきポイントを理解したうえで、実際にコミュニケーションスキルを高める方法を説明します。コミュニケーションが苦手な看護師も、まずはこれから述べる基本を身につけましょう。
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションを活用する
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションは人間同士の意思疎通に欠かせない要素であり、人を相手にする職業において信頼関係の構築に大きな役割を果たします。
言語的コミュニケーションは、言葉や文章を使って情報や感情を伝える方法で、書面やメールなども言語的コミュニケーションに含まれます。
非言語的コミュニケーションは、言葉を使わず、表情・視線・声のトーン・姿勢・身振り・距離感などを通じて意思や感情を伝える方法で、場面によっては言葉以上に感情や本心を伝える力があります。
非言語的コミュニケーションは言語的コミュニケーションを補完しメッセージに説得力を与えるため、2つを組み合わせながら使うとよいでしょう。
言語的コミュニケーションの具体的な手法
言語的コミュニケーションでは言葉がコミュニケーションの主体となります。そのため、患者や家族に対して何かを伝えるときは専門用語は使わず、わかりやすい言葉で要点を絞って短くまとめることが大切です。
質問の仕方も、患者の状態やシーンに応じてオープンクエスチョン(自由に答えさせる質問)とクローズドクエスチョン(短い答えで具体的な情報を得る質問)を使い分けることで、必要な情報を収集します。
注意すべきなのは、否定的な言葉は使わないという点です。看護師として伝えるべきことを伝える場面において、患者や家族の気持ちを特に配慮し、ときには患者の発言を言い方を変えて繰り返すといった意思の確認も必要になるでしょう。
非言語的コミュニケーションの具体的な手法
非言語的コミュニケーションには、言葉を使わずに感情や意図を伝えるためのさまざまな手法があります。
・穏やかな笑顔で安心感を与える
・聞きやすい声のトーンを意識する
・はっきりとした発音で会話する
このような方法は、患者の理解を得やすいコミュニケーションにつながります。
また、緊急時の場面でも下記のような非言語コミュニケーションを取り入れると良いでしょう。患者の緊張をほぐす効果が期待できます。
・穏やかな表情で落ち着きを伝える
・視線を合わせて関心や誠実さを示す
・優しく触れる
・頷きなどのジェスチャー
しかし、最初から距離感が近すぎるといった不必要な接触は、不安や恐怖を与えてしまう可能性があります。適度な距離を保ちつつ、目線を合わせたり少し前傾したりと、患者に寄り添う姿勢を示すようにしましょう。
看護に役立つコミュニケーション技法を取り入れる
コミュニケーションスキルを高める方法として、具体的なコミュニケーション手法を会話に取り入れることもお勧めです。
さまざまな種類がありますが、ここでは看護の現場で役立つコミュニケーション手法である、ペーシング法、ミラーリング法、バックトラッキング法、NURSEの4つをピックアップして説明します。
ペーシング法
ペーシング法は、心理学用語でカウンセリング技法の一つとして知られ、ラポール(信頼関係)を形成する有効なスキルです。相手の話し方や態度、感情に合わせて「会話の流れ」に焦点を当てながらコミュニケーションを図ります。
※ラポール:フランス語で「架け橋」という意味。自分と他者との間に橋を掛けるように信頼関係を築くこと
具体的な例は以下の通りです。
・相手の話す速度、声のトーン、声の大きさを合わせる
・相手の呼吸や相槌に合わせる
・相手の表情やしぐさをまねする
・相手が使う単語などをさりげなく会話に取り入れる
ただし、過剰なペーシングはわざとらしく感じられるので、相手に気づかれない・相手をコントロールしようとしないように実践することがポイントになります。
ミラーリング法
ミラーリング法は、相手の話し方や動作、表情などをまねる手法のことです。「身体的な共感」に重点を置きながら非言語面をまねるという特徴があり、ペーシング法の一つとされています。
相手の仕草・表情・頷き・座り方・ジェスチャーをさりげなくまねることで、相手に行為や親近感を抱かせることができます。例えば、表情でいうと相手と同じタイミングで笑うといった工夫が挙げられます。
ただし、あからさまに不自然な真似をすると相手に不快感を与える原因となるため、自然な範囲で模範するようにしましょう。
バックトラッキング法
バックトラッキング法は、相手の発言をそのまま「オウム返し」することで、理解や共感を示すコミュニケーション手法です。
相手の言葉を同じように繰り返すことで安心感や信頼関係を築き、「大切にされている」という自己肯定感を高める効果があります。
ポイントとしては、相手の言葉をあまり変えないという点です。例えば、相手が「つらい」と感情を口にした場合、「つらいんですね」と言葉を変えずに繰り返します。
また、バックトラッキング法には、話の内容を要約して返すという方法もあります。要約する際も相手の話から重要な言葉をピックアップし、なるべく言葉の表現を変えないよう意識しましょう。
注意点として、単純に繰り返すだけでは「馬鹿にしている」と勘違いされることもあるので、相手の気持ちに共感しながら自然に行うことが必要となります。
NURSE(ナース)
看護師が患者や家族に寄り添った看護をするためには、患者と家族の意思や感情を理解する必要があります。今回紹介する「NURSE」というコミュニケーション手法は、がん患者やターミナルケアの現場で注目されるスキルです。
相手の感情を言語化し、感情や置かれている状況を理解しながら敬意を示す。さらに、その感情に対して支援したいと相手に表明し、より具体的に掘り下げていくという流れがNURSEの基本となります。
① N:Naming(感情を言語化)
患者がいま、どのような感情を抱えているのか具体的な形容詞で命名する。
例:「(痛みがつらくて)イライラされているようですね」
② U:Understand(理解する)
患者が抱えている感情に対して、理解できるということを示す。
例:「そのような痛みを経験されて、さぞ辛いと思います」
③ R:Respect(相手に敬意を示す)
感情を理解しつつ、相手の姿勢や態度、人格などに対して敬意を示す。
例:「そのように辛い痛みがあるにも関わらず、いままで頑張って治療を続け、さらに自身の身の回りのこともきちんとしてきたなんて、すごいですね」
④ S:Support(支持する)
理解、敬意を示し、患者に対して「私はあなたを支援したい」ということを伝える。
例:「私とその他スタッフがいつでも、あなたの苦痛を和らげるために協力します」
⑤ E:Explore(掘り下げる)
患者の感情に焦点を当て、質問をしながらさらに情報を収集していく。
例:「その痛みによってどのように困っていらっしゃるのか、よかったらもう少し教えてもらえますか?」
NURSEは、がん患者だけでなく一般病棟や急性期、在宅の現場でも活用でき、患者の意思決定支援の場面で特に有効なスキルです。
参照:一般社団法人 日本在宅医療連合学会「がん疾患の在宅医療人材育成講座 領域2コミュニケーション P4」
コミュニケーションを円滑に進めるコツと看護師の心構え

コミュニケーションを円滑に進めるためには、相手の話をしっかりと聞き、立場や背景を尊重することが重要になります。相手を尊重したうえで自分の考えを交えながら対話を進めることで、否定的に捉えられにくくなるでしょう。
また、意識的にコミュニケーションの時間をつくることも大切です。看護師は多忙な日々を過ごしますが、その中であっても、挨拶など日常生活におけるさりげない場面での穏やかな笑顔や適度なアイコンタクトは患者に安心感を与えますし、話しかけやすい雰囲気にもつながります。
もちろん笑顔でいることが一番ですが、ときには患者や家族と悲しみを共有することも看護には必要です。負の感情がすべて悪いわけではなく、患者に「あなたを大切に思っている」と伝えられるような行動を意識することが大切になります。
コミュニケーションの引き出しは時間をかけながら経験することで自然と増えていきますので、焦らずに一つひとつの壁が経験になると前向きに捉え、乗り越えていきましょう。
さまざまなポイントを説明してきましたが、実践しやすく効果も大きいのが「自然な笑顔作り」です。下記の記事では、笑顔の効果や自然な笑顔の作り方を紹介しているので、合わせて参考にしてみてください。
【関連記事】
看護師に伝えたい笑顔の効果とは?作り笑いでもメリットあり!?
まとめ
この記事では、看護の現場で活用できるコミュニケーションの方法や、患者やスタッフとのコミュニケーションスキルを高めるためのポイントについて紹介しました。
誰でもコミュニケーションには迷うものです。相手の気持ちを理解しようとしても、言葉の選び方や伝え方に悩むことは少なくありません。しかし、迷うことは相手を思いやる気持ちの表れでもあります。大切なのは、完璧なコミュニケーションではなく、相手に寄り添おうとする姿勢です。
この記事を読んでくださった方々が、少しでもコミュニケーションにおけるヒントにしていただけたら幸いです。
この記事をシェアする
あわせて読みたい
人気記事ランキング
ALL
週間
タグから探す
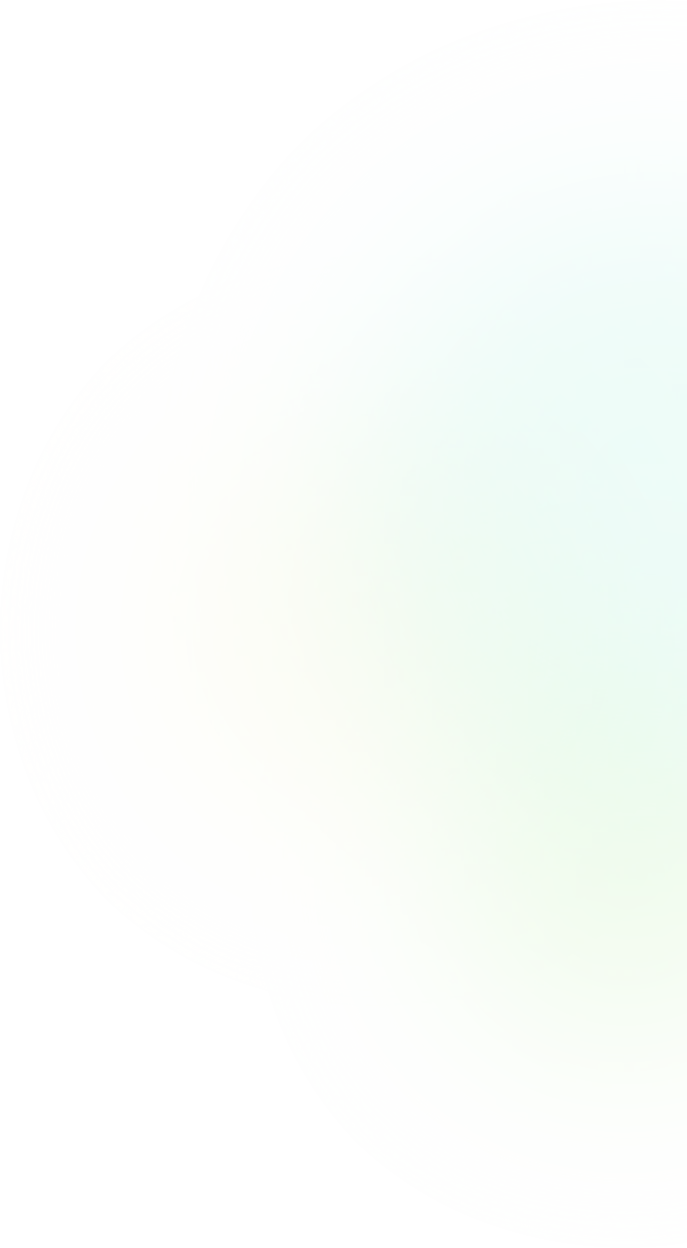
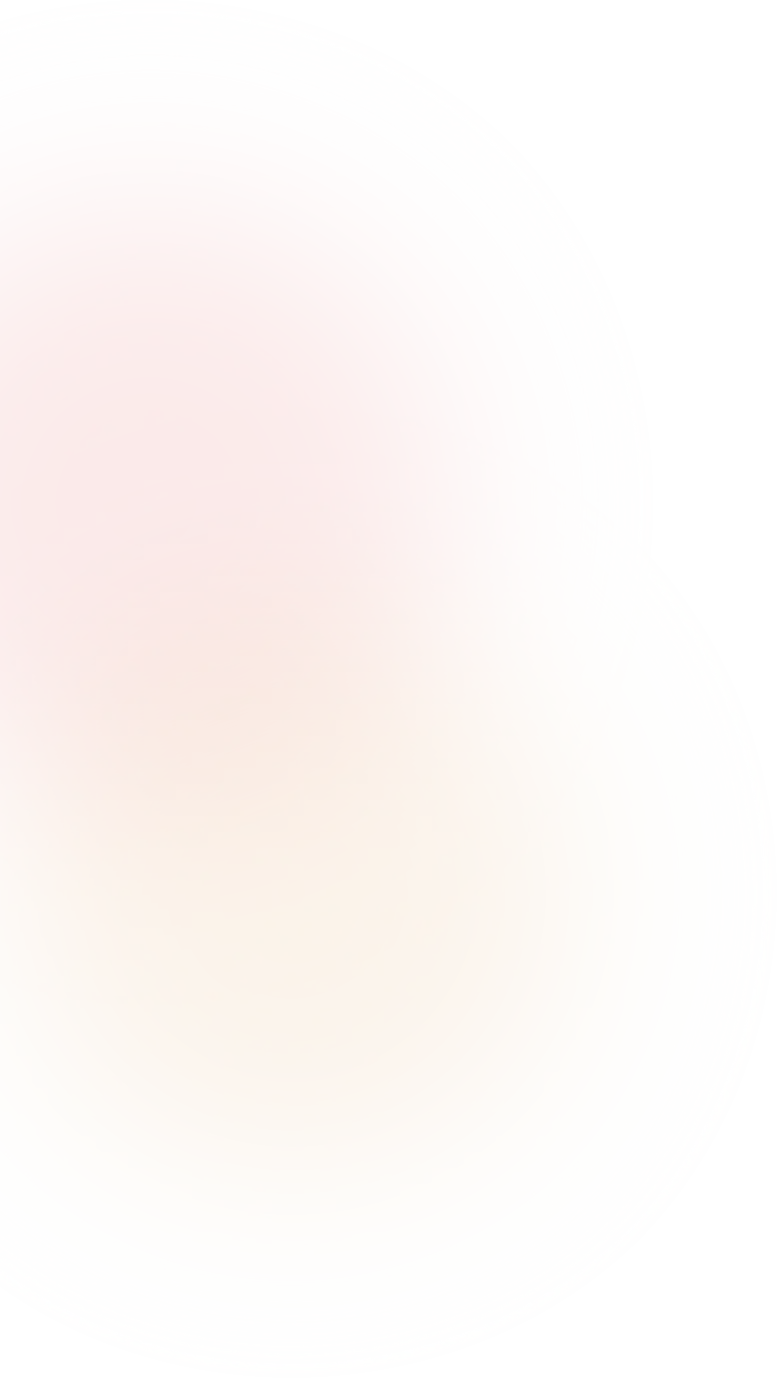












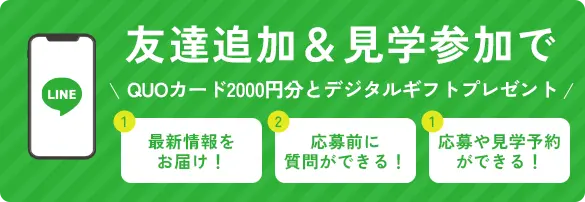


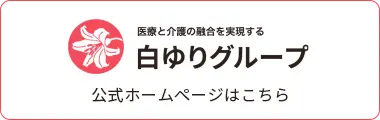
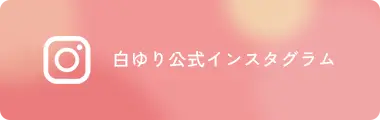
編集部
訪看オウンドメディア編集部
訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。
ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。