お悩み解決室
公開 / 最終更新
【看護師必見】夜勤をしながら生活リズムを整えるコツ!原因や心身への影響も解説

日勤と夜勤を繰り返す交代勤務は、生活リズムが不規則になりがちです。そのため、身体に不調を感じながら夜勤を続けている看護師も多いのではないでしょうか?
夜勤がきついと感じるのは、私たちの身体に備わっているサーカディアンリズムに逆らった活動をしているためです。サーカディアンリズムは「日中は活動して、夜は眠り休息をとる」といった基本的な1日のリズムを作り出しますが、夜勤によってこのリズムが崩れると睡眠障害や慢性疲労など、さまざまな影響が出てしまいます。
今回は、夜勤による生活リズムの乱れが心身に及ぼす影響や、夜勤をしながらでも生活リズムを整えるための工夫や心がけを紹介します。
2分でわかる!白ゆり訪問看護の働き方
目次
生活リズムを整える重要性とは?

ほとんどの生物は、地球の自転とほぼ同じ24時間周期のサーカディアンリズムに沿った体内時計を持っています。体温や血圧の調節、ホルモンの分泌、自律神経の調節などの生命活動は、この体内時計に大きな影響を受けています。
ところが、私たち人間の体内リズムは約25時間と、1日24時間より1時間長いことがわかってきました。そのため、少しの生活リズムの乱れが体内時計のズレへとつながり、夜型へと傾きやすくなってしまいます。
体内時計がズレると、自律神経が乱れ、疲れがとれない・眠れない・イライラしやすいといった不調をきたす可能性が高まるため、生活リズムを整えることは心身の健康を保つために非常に重要といえます。
看護師の生活リズムが崩れる3つの理由

看護師の生活リズムが崩れる大きな原因には、下記の3つが挙げられます。
・夜勤
・交代制勤務
・長時間の時間外労働
それぞれを詳しく説明します。
夜勤
患者の命を守るために必要な夜勤ですが、本来はリラックスして身体を休めるべき時間帯に仕事をする、つまり体内時計に逆らった行動をしているために体内リズムが乱れる原因の一つとされています。
仮眠によって多少は緩和されますが、夜勤はスタッフの数が少なく、急変やトラブルが発生すると休憩が取れないケースもあります。また、休憩に入っても、仕事との気持ちの切り替えが上手くできず、「仮眠をとりたいのに眠れない」といった看護師も少なくないでしょう。
仮眠が十分に取れないと、夜勤明けに急激な眠気に襲われて長時間寝続けてしまい、「今度は夜に眠れない」といった生活リズムの乱れにつながりやすくなってしまいます。
不規則な交代制勤務
病院で働く看護師の勤務体制は、2交代制もしくは3交代制などのシフト制が多く採用されています。日勤と夜勤の交代制勤務は、働く時間や寝る時間、起きる時間が不規則になるため、生活サイクルが乱れやすくなります。
特に3交代制勤務の場合は、日勤・準夜勤・夜勤の3パターンが繰り返されるため、勤務のサイクルによっては生活リズムを取り戻すのに苦労するでしょう。
長時間の時間外労働
看護師の仕事は、肉体労働・精神労働を同時に求められるため、身体も心も疲労しやすく、回復のためには十分な休息が必要です。
しかし、慢性的に人手不足な状態の病院などでは、勤務時間内に業務が終わらず、残業が常態化してしまっていることもあります。
残業で帰宅が遅くなると、食事の時間や就寝時間が不規則になるります。それが常習化してしまうと、一定のサイクルで生活することが難しくなり、生活リズムの乱れにつながってしまいます。
生活リズムの乱れが心身へ及ぼす影響は?

生活リズムの乱れは、睡眠障害や生活習慣病のリスクを高めてしまうなど、健康に大きな影響を及ぼす可能性があります。
いつもより夜更かしした翌日は、身体がだるかったり、頭がボーっとして集中力が続かないと感じたことはありませんか?
就寝時間が少しずれるだけでも生活リズムが崩れてしまい、心身の状態に作用してしまいます。ここでは、生活リズムの乱れが及ぼす影響について詳しく説明します。
睡眠障害
睡眠と覚醒のリズムには、メラトニンとセロトニンという2つのホルモンが大きく関わっています。
睡眠ホルモンとも呼ばれるメラトニンは、起床から15〜16時間後に増え始め、睡眠に向けて心身をリラックスモードに導く作用があります。一方でセロトニンは、日光を浴びることで分泌量が増えるホルモンで、メラトニンの原料となります。
夜勤で生活リズムが崩れることで、これらの睡眠に関わるホルモンの分泌が抑制されてしまい、寝つきの悪さや中途覚醒、寝ても疲れが取れないなどの睡眠障害を引き起こす可能性が高まります。
病気への免疫機能が低下する
免疫機能を高めるには、十分な睡眠やバランスの良い食事、適度な運動など、規則正しい生活習慣が大切です。そのため、夜勤による睡眠不足、食生活の乱れなどは身体にとって大きなストレスとなり、免疫力の低下につながってしまいます。
また、免疫には腸内細菌も深く関わっているため、深夜の食事など不規則な食生活によって腸内環境が乱れてしまい、免疫機能の低下が生じやすくなります。
疲れがとれない
質の良い睡眠やバランスの良い食生活は疲労回復に効果的ですが、夜勤をしていると睡眠不足や不規則な食事など、疲労の回復を妨げる行動が多くなってしまいます。
夜勤で削られた睡眠時間を昼間の仮眠でカバーしようと考える方もいるかもしれませんが、昼間に長時間眠ってしまうことで、頭がボーっとしたり、夜間に寝付けなくなったりと、疲労回復に逆効果となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
日勤と夜勤が繰り返される勤務の場合、数日かけてやっと整い始めた生活リズムが夜勤でまた乱れてしまうことになり、身体が常にだるいなどの慢性疲労の原因となるのです。
太りやすくなる
「夜勤を始めたら太りやすくなった」と感じている看護師もいるのではないでしょうか?
通常、私たちは食事からエネルギーを補給し、日中に活動することで消費します。そして、夜間は自律神経やホルモンの働きによってエネルギーの消費が抑えられ、過剰となった分は身体に蓄積されやすくなります。
夜勤時の夜食には、おにぎりやパン、カップ麺など手軽に食べられる食品を選ぶ場合も多く、これらはバランスの良い食事内容とは言えません。このような食事内容に加え、早食いや食事と睡眠の時間帯、運動不足などが原因で太りやすくなると考えられます。
感情が不安定になる
昼夜逆転の生活を続けていると交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズにいかず、自律神経に不調が出やすくなります。
些細なことでイライラしたり、気持ちが落ち込んだり、感情が不安定になるのは不規則な生活習慣が原因かもしれません。このような精神的な落ち込みは、ときにうつ病などの精神疾患のリスクを高める原因にもなるので要注意です。
看護師が夜勤をしながら生活リズムを整えるコツは?

夜勤は体内時計に逆らう活動であり、健康的とは言えない働き方です。ですが、患者が安心して治療を受けるためにも24時間医療サービスを提供する体制は欠かせないもので、病棟で働く以上は対応していかなければなりません。
看護師はできる範囲で自己管理をし、なるべく体調を崩さずに夜勤を続けていく必要があります。それには、夜勤前後の過ごし方や夜勤中の食事・睡眠の取り方が重要です。
「体内時計に合わせた生活リズムを取り戻す」という意識で行動するだけでも、自律神経やホルモンバランスが整いやすくなり、体調の改善につながりやすくなります。
夜勤前の寝だめをしない
夜勤を乗り切るために、夜勤前に寝だめをしている方は多いのではないでしょうか?
不足している日頃の睡眠時間を確保しようと寝だめをしても、実際に眠りをためることはできず、かえって睡眠の質を下げることになりかねません。それよりも、生活リズムに合わせた睡眠習慣を見直す方が、疲労回復につながりやすくなるでしょう。
サーカディアンリズムに沿った理想的な睡眠のとり方から考えると、体温が低下して睡眠に適した体内環境となる22〜翌6時ころに仮眠をとることが質の高い睡眠に効果的とされています。そのため、夜勤前は寝だめするよりも昼と夜のメリハリをつけて生活し、夜勤中に適切な仮眠をとる方が生活リズムを乱さずに過ごすことができます。
夜勤前に眠気を感じる場合は、2時間程度の仮眠を取ります。この際、最も眠りにくくなる午後7時は避けるようにしましょう。
参考:日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」
参考:斉藤良夫,佐々木司著「病院看護婦が日勤-深夜勤の連続勤務時にとる仮眠の実態とその効果」
参考:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」
夜勤中は10分でも仮眠をとる
夜勤中は、休憩の直前までバタバタと忙しく動き回って仕事をしている日もあります。憩に入ってもすぐにリラックスモードに切り替えるのは難しく、仕事への不安から「頭が冴えてしまって眠れない」という方も少なくないでしょう。
睡眠は、眠りに入ってから覚醒に向けた時間まで1サイクル2時間と言われています。連続2時間の仮眠は、眠りの浅い「レム睡眠」の状態から目覚めることができるため、覚醒時のだるさ(寝ぼけ状態)を軽減する効果も期待されます。
2時間の仮眠が難しい場合でも、できる限り仮眠をとるようにしましょう。10分程度の短時間であっても、疲労の回復に役立つとされています。
夜勤明けの睡眠は午前中にとる
夜勤明けの睡眠のとり方も生活リズムを整えるためには重要です。夜勤明けは、午前中に2時間程度の仮眠をとり、昼には起きて活動を始めることで、体内時計をリセットしやすくなります。
夜勤明けは、日光の刺激で脳が覚醒しないよう帽子やサングラスなどで陽光を遮断、早めに帰宅してベッドに入るようにします。入眠前のSNSチェックは脳が覚醒してしまうため控えた方が良いです。寝付けないときは、カーテンやアイマスクなどで光を遮断するなど、睡眠環境を整えるようにしましょう。
2時間程度の仮眠をとった後は、カーテンを開けて太陽の光を取り込み、疲れが残らない程度にいつも通りの活動を心がけます。さらに、夜は早めに休むようにすると夜勤でズレた体内時計のリズムを修正しやすくなります。
夜勤中の食事は内容とタイミングを意識する
食事のタイミングは、普段の食事時間に近づけることがポイントです。夜勤時も出来るだけいつもと同じ時間に食事をすることで、体内時計に合わせたリズムを保つことができます。
夕食は深夜帯を避け、19〜22時頃までにとるようにします。深夜の高カロリーな食事は胃腸障害や生活習慣病のリスクを高めてしまうため、避けた方がいいでしょう。
食事の内容は、おにぎりやパンなど手軽な食品で済ませてしまいがちですが、サラダや野菜スープを加えるなどバランスの良い食事が理想的です。
疲れたときは心身を休めることを優先

生活リズムを整える大切さは理解していても、実践するのはなかなか難しいと感じている人もいると思います。
「眠らなくては」と思えば思うほど焦って眠れなくなるのと同じように、「生活リズムを整えなくては」と意気込みすぎると逆効果となってしまう場合もあるのです。そのため、疲れた時はあれこれ考えずに、心身を休めることを優先してください。
しっかり休んだ後は、自分が好きなことや心安らぐものに取り組むことで、メリハリのある生活へ切り替えができ、気分転換にもなります。
散歩やヨガ、ストレッチなど疲労回復にも効果があるとされる運動を取り入れることで睡眠の質を向上させると共に、生活リズムの改善にも効果的なので試してみるのも方法の一つでしょう。
生活リズムを整えるには日勤で働ける職場への転職もおすすめ
夜勤が原因の不調が続いている場合は、働き方について見直す必要があるかもしれません。
看護師の資格を活かしながら夜勤なしで働ける職場は意外に多く、例えば、訪問看護やクリニック、デイサービスや検診センターなどが夜勤なしで働ける職場として挙げられます。
このような職場では夜勤なしで働けるという特徴以外にも、休日が固定されているなどワークライフバランスを考える上でもメリットがあると言えるでしょう。
訪問看護リハビリステーション白ゆりは、勤務時間8:30~17:30の日勤帯/固定休みで働くことができます。訪問看護の働き方に興味がある方は、下記の記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
訪問看護の仕事内容!病棟より大変?働くメリット・デメリット、やりがいも解説
夜勤を辞めたい…原因と対処法は?日勤で働ける転職先も紹介
まとめ
夜勤は医療現場には必要ですが、働く看護師の生活リズムが乱れやすく、身体にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。時に睡眠障害や生活習慣病など人生に関わる大きな不調をきたす恐れもあるため、注意が必要です。
夜勤による不調を感じている方は、ぜひ本記事で紹介した生活リズムを整えるための工夫を取り入れてみてください。
夜勤が心身に与える影響は、職場環境や年齢、体力、健康状態などの個人的な要因によっても差があります。負担が大きすぎる場合は、夜勤のない職場に転職するのも一つの方法です。仕事もプライベートどちらも充実した健康的な生活を送るために、働き方について見直してみませんか?
訪問看護リハビリステーション白ゆりでは札幌市内で働ける訪問看護師を募集中です。詳しい求人情報は下記の内容をご確認ください。職場見学会の申し込みも随時受付中です。
この記事をシェアする
あわせて読みたい
人気記事ランキング
ALL
週間
タグから探す
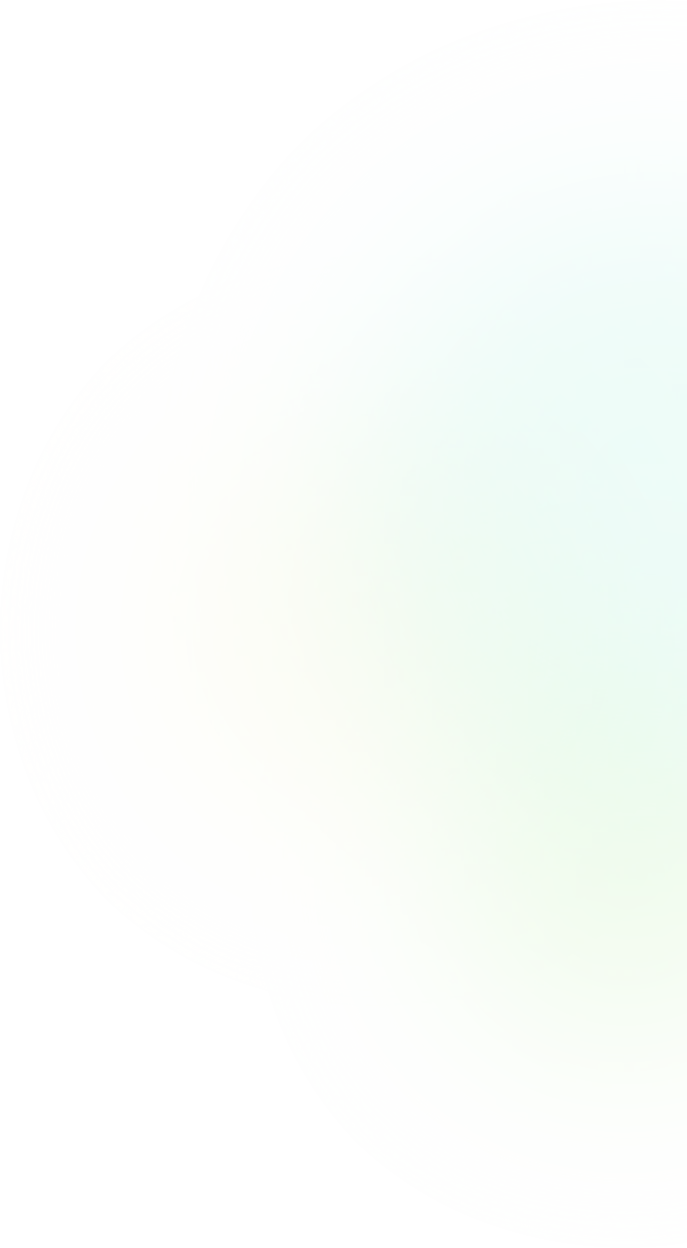
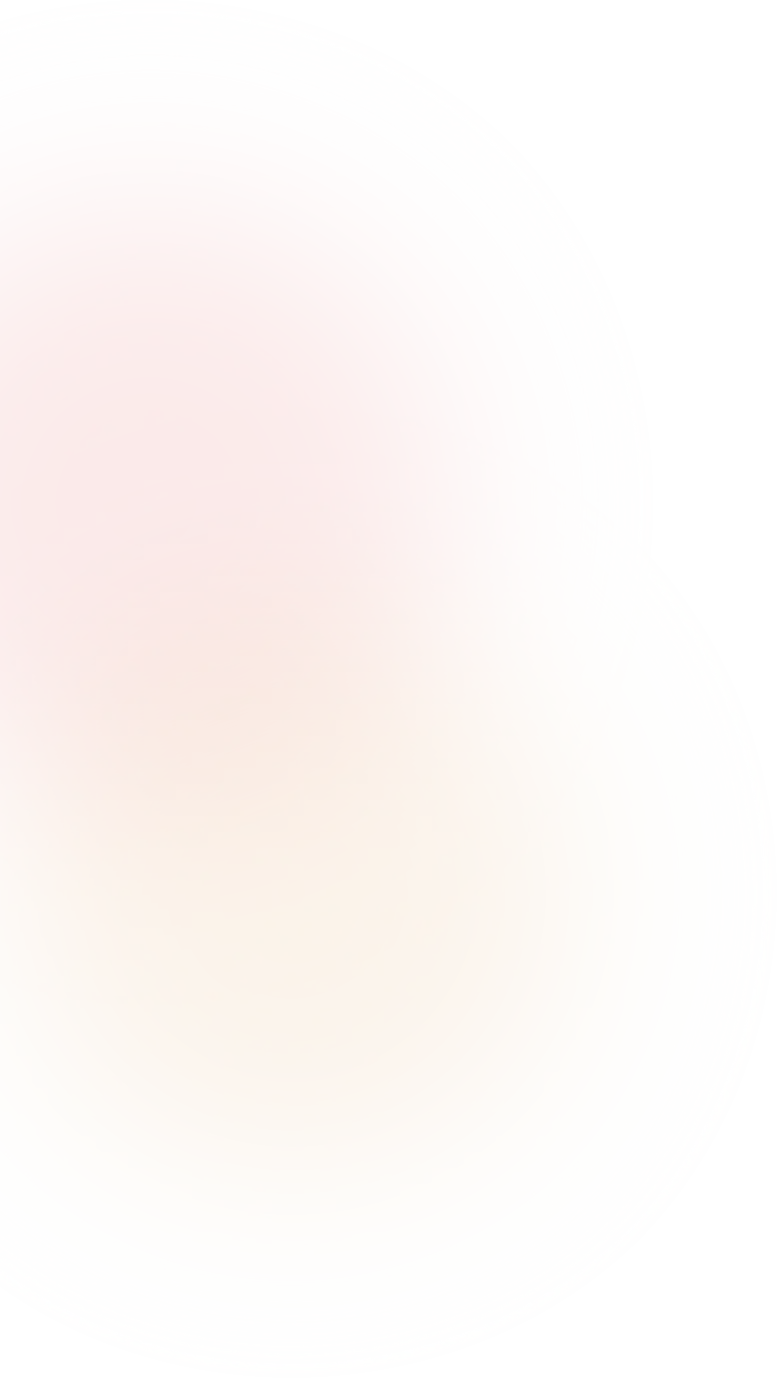












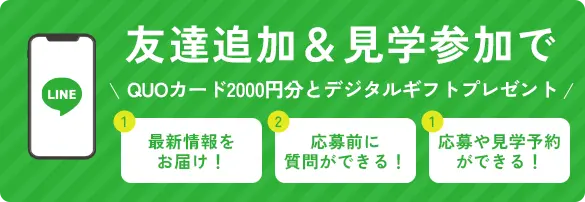


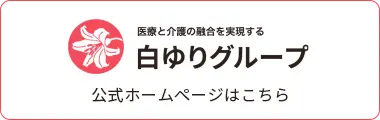
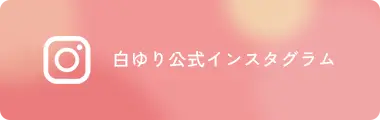
編集部
訪看オウンドメディア編集部
訪問看護師として働く魅力をお伝えすべく、日々奔走する白ゆりのWebメディア担当。
ワークとライフに役立つ記事を中心に、訪問看護に関するさまざまな情報を発信しています。